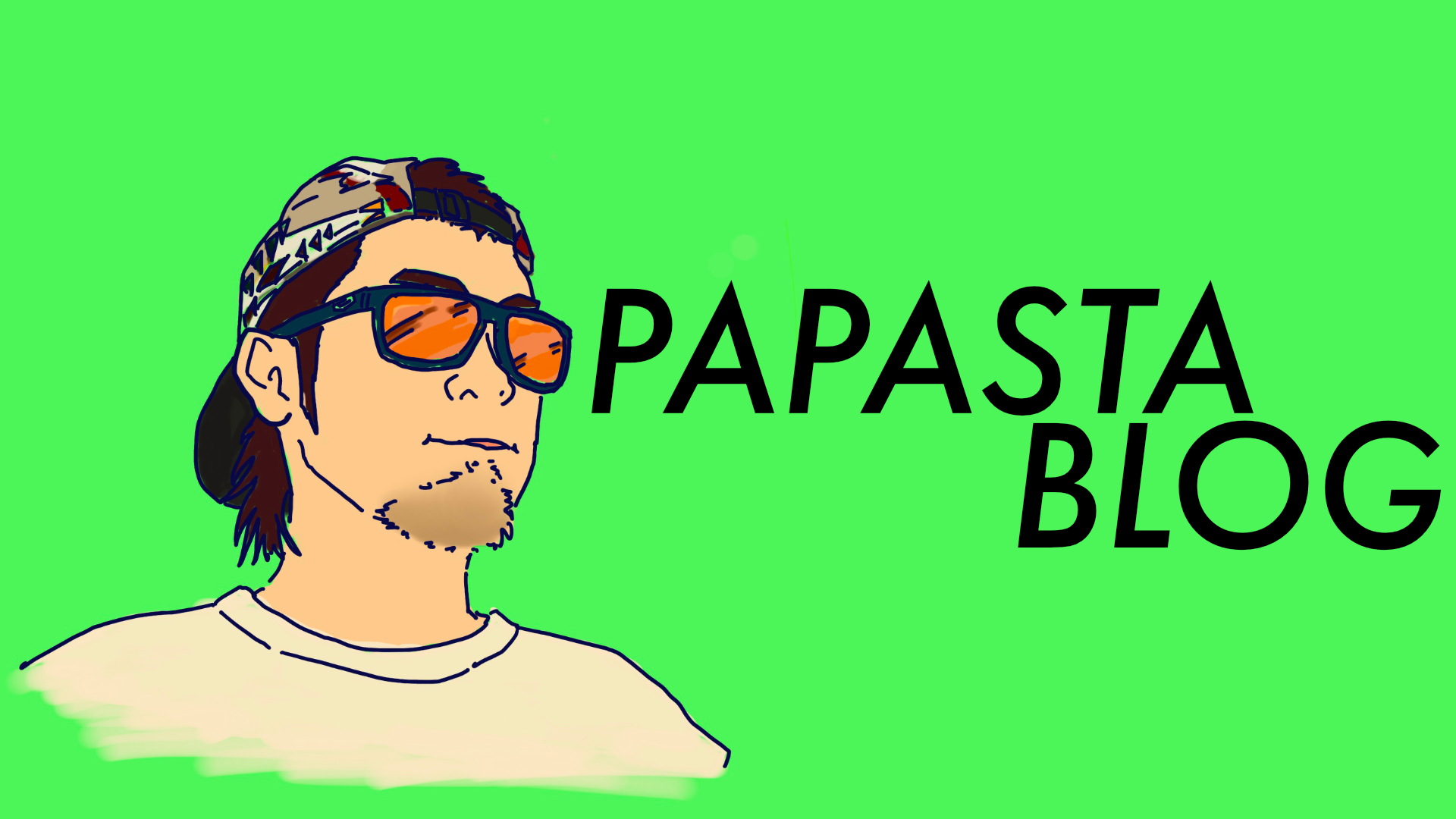2026年1月27日、火曜日。
義祖母が亡くなった。
先ほど、葬儀場との打ち合わせを終えて一息ついたところだ。
ここ4ヶ月で、身近な人を見送るのは2人目になる。
短期間にこれほど葬儀が続くと、
人は強制的に「死」というイベントの運営に詳しくなってしまう。
だが、その経験値は今、家族を守るために使うべきものだ。
娘婿の役割は「一緒に泣くこと」ではない
徹底した「黒子」に徹する
今回の葬儀において、私が自分に課した役割は明確だ。
妻と義母を支える「黒子(くろこ)」であること。
愛する人を失った時、遺族は悲しむと同時に、膨大な「決定」と「手続き」に追われる。
・参列者のリストアップ
・香典返しの選定
・役所への届出
これらは、悲しみの淵にいる人間にとっては暴力的なほどのストレスだ。
だからこそ、私が動く。
運転手、飲み物の買い出し、親戚への連絡、受付の準備。
あらゆる雑務(ノイズ)を私が吸収し、
妻と義母には「故人と向き合う時間」だけを残す。
それが、今の私にできる最大の供養であり、愛だと思っている。
経験が「余裕」を作る
4ヶ月で2回目という現実
皮肉なことだが、
4ヶ月前の葬儀の記憶が新しいおかげで、流れが手に取るように分かる。
「次はこれが必要になる」
「ここで休憩を入れないと倒れる」
先回りして動ける自分がいる。
悲しい経験だが、無駄にはなっていない。
この「葬儀リテラシー」のおかげで、慌てふためくことなく、
どっしりと家族を支える柱になれている。
まとめ:安心して泣ける場所を作る
悲しむ役目は遺族に任せ、夫は環境を整える「黒子」になる。雑務を引き受けることが、最大のサポートだ。
もし身近に不幸があった時、周囲ができることは「言葉をかけること」だけではない。
「お茶を買ってくるよ」「車を出そうか」
その具体的な行動一つが、遺族の心の荷物を一つ降ろすことになる。
次回は、葬儀の合間にふと考えた「残された時間の使い方」について。
死を身近に感じることで、逆説的に「生」の解像度が上がる瞬間の記録。